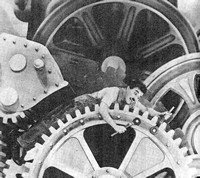話題:連載創作小説
気がつくと彼女は名曲喫茶【平均律】のドアに手をかけていた。手のひらに真鍮の冷たい感触が伝わる。そのままゆっくり扉を引くと、カランカランという乾いたドアベルの音色が優しく辺りに響き渡った。
久しぶりに足を踏み入れた【平均律】の店内は、以前訪れた時と全く変わりのない姿を見せていた。時代を錯覚したような古めかしい椅子やテーブル、床や壁に染み込んだ年月が独特の芳香を放っている。
ぽつぽつと離れて座る客たちも現代の流行など“どこ吹く風”といった有り様で、それぞれが自由に本を読んだり物思いに耽っていたりと、気ままな時間を過ごしている。
彼女はさり気なく店内を見渡した。が、青年の姿は何処にもない。
やがて彼女が窓際の片隅の席を選んで座ると、水の入ったグラスを持ったマスターが静かな足取りで注文を取りにやって来た。
名曲喫茶【平均律】のマスターは穏やかさを絵に描いたような初老の痩せた男性で、黒い丸眼鏡の奥では小さな瞳が優しげな光を放っていた。
彼女はエスプレッソを頼んだ。
それから思い出したように雨で少し濡れている外套を脱ぎ、それを丁寧に折りたたんだ。そして、濡れている部分が上になるようにして向かい側の空いている椅子の上に置いた。
店内にはフランツ・リストの《ため息》が流れている。
質のよい大型のスピーカーから最適な音量で流れてくるリストのピアノ曲は、聴く者の心を魅了するに十分なものだった。
流石に名曲喫茶と銘打つだけの事はある。恐らくはスピーカーの配置も、客がどの席で聴いても曲の良さが損なわれないよう計算されているのだろう。彼女はすっかり感心していた。
同時に、二十歳の頃の自分がこの店を知っていたなら間違いなく通いつめていたに違いない、とも思った。
彼女は三歳からピアノを始め、半ば英才教育に近い形でそのまま音楽学校へと進んだ。将来はピアニストとして世界へ羽ばたく事が彼女の幼い頃からの夢であったし、当然そうなるものだと信じてもいた。
しかし、現実はそう甘くない。彼女がピアニストになる夢を諦め、一般の会社に就職したのが二十五歳の時。それは彼女がこの街で暮らし始めた時期でもあった。
現在の彼女は音楽とは無関係の事務の仕事をしている。彼女の心は音楽と一定の距離を保とうとしていた。
それで彼女は、この名曲喫茶の存在を知った後も意識的にそれを遠ざけてきたのだった。…あの日、雨のテラスに美しい青年の姿を見る迄は。
もしかしたら、雨の日の喫茶店という場所は、忘れかけていた記憶を呼び覚ます性質があるのかも知れない。
彼女は、リストの《ため息》を聴きながら、自分がまだピアニストを目指していた頃を思い出していた。
すると、不意に妙な感覚が彼女を襲った。
それは、あの美しい青年と彼女の中にある何かとを結びつけた。時計の長針と短針が十二時に重なり合うように、その二つは瞬間ピタリと彼女の中で重なり合った。
彼女の中で確かに何かが起こっていた。しかし、それが何なのか、それが判らない。
その時、テーブルにコトリと珈琲カップが置かれる音がして、彼女の思考は中断された。
「ごゆっくりどうぞ」
マスターは丁寧な口調でそう云うと、くるりと彼女に背を向けた。
「あ、あの…」
背中を呼び止められ、マスターが振り向く。
彼女は、あの青年について何か知っている事はないか、マスターに訊ねるつもりだった。しかし、どう切り出して良いのか判らない。彼女は自分から呼び止めておきながら、黙りこんでいた。けれども、マスターは柔和な笑顔を崩す事なく彼女が次に口を開くのを待ち続けてくれた。
これがもし客の回転率の高い簡易型のカフェ店舗であったなら、彼女の焦れったい態度に少なからず店員は苛立ちを見せていたかも知れない。そして、至近席の客たちも怪訝な眼差しを彼女に注いだ事だろう。
けれども、此処はそういう場所ではない。客が急き立てられるように時間に合わせるのではなく、時間の方が客のテンポに寄りそうように流れている。そういう特異点とも云うべき世界だ。
また、座席と座席の間に適度な距離をもつ空間があるお陰で周囲の目を気にする必要もない。
そんな店内のゆったりとした空気とマスターの落ち着いた態度、そして流れ続けるリストの《ため息》が、彼女の肩から不要な力と緊張を取り除いてくれた。
自らのテンポを取り戻した彼女は、自分でも驚くほど自然に話を切り出していた。
緩やかに流れる時間の川に、言葉の舟をそっと浮かべるように。
〜4へ続く〜。