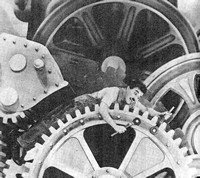話題:連載創作小説
美しい青年だと思った。
奇跡とも云うべき完璧な左右対称バランスを得た顔は、滑らかな櫛どおりを持つ金糸のような細くて美しい髪に縁どられ、また、透き通るように白い肌は初秋の訪れを告げる風にも似た涼やかな温度を、その表面に或いは皮下の内に湛えていた。
物静かな情熱を宿した柔らかな口唇は愛を囁くにこそ相応しい天からの賜り物であり、極めて身綺麗に着こなされた着衣は少しも生活の匂いを吸着してはいないようだった。
疑いようもない美しさ。けれども、その非現実的とも云える美しさの中には何処か深い哀しみにも似たある種の切ない情感が宿っているように思えた…。
彼女が初めて青年の姿を見たのは十月の暮れの喫茶店で、少し冷たい雨が降っていた。
名曲喫茶【平均律】は小ぢんまりとした店ながら、蔦に覆われた建物の外壁の更に外側、表通りに面した小庭にも数席のパラソルを備えたテーブルがあり、名曲喫茶には珍しくオープンスタイルカフェの形を取っている。
いや、珍しいと云えば名曲喫茶という存在自体がかなり珍しい。クラシックのレコード盤がまだ高価で入手し難く、また、個人で収集するには(入手ルートなどの流通の問題で)限界のあった時代、人々が家ではなかなか聴く事の出来ないクラシック音楽をゆっくり楽しむ為の場として名曲喫茶は誕生した。それが1950年頃。1960年代には芸術家志向の人間が集う知的ファッショニズムの場として隆盛を極めるも、以降、レコード盤の普及に伴って一種のサブカルチャー的存在へと変わり、やがて徐々に衰退してゆく事となる。
現代では幾らかその存在が見直され始めているとは云え、街を歩いていて普通に名曲喫茶を見かける事は殆んどないと云っていい。そういう意味では、この【平均律】は日常的現代風景における特異点のような存在であった。
日常習慣的に彼女は、仕事が終わると手早く帰り仕度を済ませ仕事場を後にする。そしてこの名曲喫茶の前を決まって午後五時半に一人で通る。そういう意味では、その喫茶店は彼女にとってはよく知る店と云う事も出来た。
もっとも、馴染みの店かというと実はそうでもない。彼女はこの街に移り住んでもう七年になるが、その間、この名曲喫茶【平均律】に足を踏み入れたのは、たったの一度きり。要は、そこに青年の姿を見る迄、その喫茶店は彼女にとって見慣れた帰り道の風景、単にその一部に過ぎなかった。
彼女が青年に目をとめたのは、いつもの見慣れた風景に感じた微かな違和感のせいだった。
絹糸のような細い雨が絶え間なく降り続く中、その青年はたった一人でオープンテラスの席に座っていた。舗道に落ちた雨粒から上がる小さな飛沫が霧のように街のあしもとを覆っている。
軒から張り出したヨーロッパ風の庇と大きめのパラソルが雨避けになるとしても、このような日にわざわざオープンテラスの席を選ぶ人間は滅多にいない。雨に煙る街角とテラス席の客。この珍しい取り合わせこそ彼女が感じた違和感の正体に他ならなかった。
美しい青年だと思った。
その印象は、何々がどうだから美しい、と云った論理的展開を待たず瞬時に彼女にもたらされたものだった。
しかし、彼女が青年に感じたのは決してその飛び抜けた美しさばかりではなかった。
雨の街に遠い眼差しを投げかける二つの碧い瞳はその奥底に深い憂いを宿し、それは美しさ以上に切とした哀感を汚れなき瞳の湖水に浮かび上がらせていた。
そして、もう一つ。彼女が青年に感じたのは微かな懐かしさだった。この青年とは、かつて何処かで逢っているような気がする。彼女は直感的にそう思った。
しかし同時に、このような美しい青年と何処かで出逢っているならば、その記憶が鮮明さを失なうとはどうしても思えなかった。
彼女が覚えた懐かしさという感覚を、理性は何処までも冷徹に否定し続けていた…。
〜2へ続く〜。