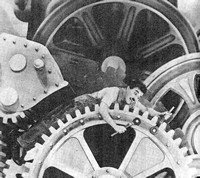話題:連載創作小説
彼女は慎重に言葉を選びながら、雨の日に必ずテラス席に座っていた青年の事をマスターに訊ねた。幸いにも、その理由について問い質されるような事はなかった。
正直、そこを突かれていたら彼女としては答えに窮せざるを得なかった。もともと、彼女と青年の間には関係と呼べるほどのものはない。けれども、あの青年はやはり彼女にとっては特別な存在だった。しかし、それを他人に上手く説明する事は限りなく不可能に近い。彼女は詮索されなかった事に内心で深く安堵しながらマスターの返答を待った。
ところが、彼の口から出てきた言葉は彼女にとって全くの意外なものだった。
マスターは、彼女の話すような青年にはまるで心当たりがないと云う。
いや、彼女とて、なにもマスターが青年の氏素性まで知っているなどとは思っていない。それでも会話の一つや二つ交わした事はあるだろうし、もしかしたら名前くらいは知っているかも知れない。少なくとも会話の中に青年に繋がる何かしらのヒントが存在する可能性もある。そういう意味で彼女は訊ねていた。
しかし、マスターは「この店でそのような青年の姿を見かけた事はない」と、青年の存在そのものをきっぱりと否定したのだった。
そんな馬鹿な話はない。
彼女はこれ迄、雨の降る日に何度も青年の姿を見かけていたし、あれほどの美しさを持つ青年だ、印象に残らないわけがない。
彼女はもう一度同じ質問を繰り返した。しかし、返ってきた答えは先程と全く同じものだった。
表情や話ぶりを見る限り、マスターが嘘をついているとは到底思えない。そもそも、嘘をつく理由がない。彼女が店に入ったのも青年について訊ねたのも、全ては突発的な出来事だ。それに対して咄嗟に嘘をつこうとすれば、必ず挙動の何処かに不自然な感じが出るはずだ。ところが、彼の応対にはそういう不自然さはまるでない。
しかし……彼女は考える。そうなると、あの青年は存在しない事になってしまう。それは彼女が見た現実と符合しない。つまり、両者を同時に成立させる解は世界の何処にも存在しない事になる。
予想外の展開に彼女は次なる行動の指針を失なっていた。
すると、困惑で口をつぐむ彼女にマスターから助け船となる言葉が出された。
「…もし宜しければ、他のお客さんにも訊いてみましょうか?」
マスターに拠れば、名曲喫茶《平均律》は客の殆どがいわゆる常連と呼ばれる人たちで、毎日店に来る人も少なくないという。自分は彼女の云うような青年に心当たりはないけれども、常連さんなら知っているかも知れないので訊ねてみてはどうか?と云うのだ。
無論、その申し出を断る理由は彼女にはなかった。
常連らしき客たちの間を歩き廻るマスターの姿をぼんやりと眺めながら彼女は思っていた…
自分は此処でいったい何をやっているのだろう?名前も知らない青年を探して馴染みのない店へ入り、計らずもこうして他人の手を煩わせてしまっている。もともとこれは、彼女の心の中だけのごくごくプライベートな問題であったはずだ。彼女は自分の取っている行動がまるで理解出来ずにいた。
《続きは追記からどうぞ♪》