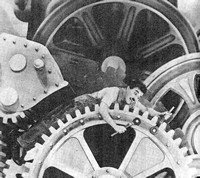話題:SS
俺は潜入捜査官。コードネームは[コハダ]。日々危険と隣り合わせに生きている。この道十年のベテランだが、神経を磨り減らすような毎日に“慣れ”の文字はない。常に崖に張られた一本のロープの上を歩いているようなもの。ちょっとした風でバランスを崩せば一巻の終わりとなる。
俺の所属する潜入捜査班は警視庁、警察庁、法務省、厚労省、そして餃〇の〇将、ジャ〇ネットた〇たという省庁や民間企業、いわゆる官民の垣根を越えた越境タッグとなっている。……と言えば聞こえは良いが、潜入捜査が禁じられている今日(こんにち。これを“きょう”と読むようでは潜入捜査官は務まらないぜ)、あくまでも非合法の部署であり、表向きは存在しない事になっている。
よって、もし俺たちに何かあったとしても国家は一切関知しない取り決めになっている。つい先立ても潜入中の仲間の一人[コードネーム:ユビキタイ(湯引き鯛)]が対立する組織の子猿たちにカメリア―つまり―椿のあの堅〜い実を7、8個もぶつけられるという恐ろしい事態が起こったのだが、その際も上は救いの手を差し伸べようとはしなかった。否、餃〇の〇将は[餃子〇皿無料券]を進呈したらしいが、その辺りの詳細は不明である。
非情だ。割りが合わない。とてもではないが好き好んでやる仕事ではないだろう。が、それでも俺がこの仕事を続けているのはひとえに使命感と正義感――ではなく、潜入捜査官という言葉の響きがカッコいいからだ。更に、俺たち潜入捜査官はそれぞれコードネームを持つが、それらは何れもお寿司のネタとなっている。それも粋で鯔背(いなせ)でカッコいい。その二つが全てだ。他に理由などない。いや、要らない。名前の響きがカッコいい。それで十分だ。
とは言え、伊達や酔狂のみでこなせる仕事ではない。この危険な任務を続けて行けるのは、頼りになるバックアップチームの存在があるからだ。彼らは常に俺たちをフォローし(勿論ツイッターもフォローしてくれている)、後方から支援してくれている。
バックアップチームは複数ありそれぞれに別個の役割が与えられている。例えば、【チーム・お百度参り】。これは俺たち潜入捜査官の安全祈願の為に神社でお百度参りをしてくれる有り難いバックアップチームだ。彼らとの面識は全くないが、誰かが自分の為にお参りをしてくれていると思うと途端に勇気が湧いてくる。
そんな数ある後方支援チームの中で最も頼りになるのが、今、俺の目の前にいる男――[コードネーム:ポンセ]――が所属する【チーム・小道具さん】だ。変装用のつけ髭やカツラ、超小型のスパイカメラなど潜入捜査に役立つ様々な特殊アイテムを提供してくれるバックアップチームだ。007で言うところのQ、名探偵コナンでの阿笠博士を想像してくれればイメージは掴めると思う。因みに彼らのコードネームは伝統的にプロ野球の歴代助っ人外国人の名前がつけられている。
ポンセ「さて、コハダ、説明は済んだかい?」
俺「いや、あと一つ残ってる」
明日は俺に取って非常に重要な一日となる。俺の潜入している組織を始め、16もの秘密結社が十年ぶりに一同に会するのだ。《秘密結社対抗大運動会》。世紀の大イベントだ。そして、その現場に警視庁、警察庁、厚労省、法務省、そして餃〇の〇将、ジャパ〇ットた〇たの選抜チームが雪崩れ込み、全ての組織を一網打尽にする。間違いなく日本の裏面史に刻み込まれるであろう作戦の決行日、それが明日なのだ。
場数を踏んでいる俺でも経験した事のないような大作戦だ。恐らくは銃弾の雨嵐が降る事になるだろう。流石に身震いがする。こういう時、最も頼りになるのが【チーム・小道具さん】だ。明日の作戦に必要な便利グッズを用意してくれている筈だ。
俺「待たせて悪かった。一応説明は終わった」
ポンセ「話が長いのはハードボイルドには似合わないぜ」
俺「ソーリー。だが、俺には読者に対して説明する義務がある。どうか解って欲しい」
ポンセ「主役はつらいな。フン、まあいいさ。では本題に入ろう。お前さんの所望は、確か、防弾チョッキだったな」
俺「ああ。近頃の若い奴は防弾ベストなんて言ったりするらしいが、その呼び名は俺にはお洒落過ぎて似合わない。俺にとってベストってのは……」
ポンセ「洒落たBARのバーテンダーが着るもの……そう言いたいんだろう?」
俺「その通り。お洒落な呼び名は俺たちには似合わない」
ポンセ「ああ。タートルネックのスウェーターやハンガーでは胃の腑が落ち着かない。とっくりのセーターと衣紋掛けだ」
俺「フッ、また随分と可愛いネタから入ったもんだな。初歩中の初歩じゃないか」
ポンセ「少し物足りなかったか?」
俺「“水着”は?」
ポンセ「海水パンツ」
俺「長方形(ちょつほうけい)は?」
ポンセ「長四角(ながしかく)」
俺「うむ、それでこそポンセだ。俺たちみたいな古い男には古い呼び名がよく似合う。だから、防弾チョッキでいい。仕事が終わったあと“直帰”出来そうな雰囲気もあるしな。まあ、ベストも“ベストを尽くせそう”で惹かれるが。二兎を追う者は一兎をも得ず、だ。と言ったところで、いい防弾チョッキは用意出来たかい?」
ポンセが顔を少し曇らせる。
ポンセ「いや、それなんだがな……申し訳ないが防弾チョッキの提供は上に止められてしまった」
俺「……何故?」
先刻も言ったと思うが、明日は恐らく銃弾の雨が降る。防弾チョッキが命綱となる事は必定だ。
ポンセ「運動会に防弾チョッキを着て参加するのは不自然だ。それで身元がバレれば敵は警戒し身構えるだろう。逆に防弾チョッキ無しの方がお前さんにとっても安全、それが上の判断だ」
ふ〜むふむふむ。言われてみれば確かにそれも一理ある。だが……
俺「……防弾アイテム無しではとても不安だ」
するとポンセは何故かニヤリと笑った。
ポンセ「そう言うと思って特殊な防弾アイテムを用意した。お前さんの為に4億円も掛けて特別に作ったんだぜ。自分で言うのも何だが、こいつはスグレモノだ」
ポンセは自信満々の顔つきで持参した紙袋から小さな箱を取り出し、開けてみせた。透明で小さな円形の物が見える。
俺「これは?」
ポンセ「聞いて驚くな、こいつは最先端科学と俺の技術の結晶である防弾……コンタクトレンズだ」
俺「……防弾コンタクトレンズ!」
そんなもの見た事も聞いた事もない。
ポンセ「ああ。世界にたった一つだけのアイテムだ。対装甲車用の銃弾を受けてもビクともしない。それどころか、遠視、近視、乱視の全てに対応している上、瞳の潤いをキープする極めて高い保湿性を持っているスグレモノだ。これなら運動会で着用していても不自然ではないだろう」
確かに。コンタクトレンズはボディーチェックの対象とはならないだろう。
俺「成る程、考えたな。しかし……」
ポンセ「そうだ」
俺「まだ何も言ってないが」
ポンセ「長い付き合いだ。お前さんの言いたい事ぐらい解るさ」
俺「そうか。で、どうなんだ?」
ポンセ「お前さんの思っている通りさ。飛んでくる弾は必ず眼球で受けるようにしてくれ。そこだけはくれぐれも気を付けるように。あとは大丈夫だ。問題ない」
やはり、そうか。飛んでくる銃弾に対して素早く眼球を当てる……。かなり高いアジャスト能力が要求される。いや、ここまで来るとアジャパー能力かも知れないが。
俺「……」
ポンセ「あ、そうそう。それともう一つ。弾を受ける時は絶対に目をつぶらないよう気を付けてくれ。残念ながら目蓋はレンズの外側なのでフォロー出来ないからな」
ポンセ。ちょび髭のポンセ。パチョレックの相棒ポンセ。
俺「素晴らしい。非常に助かる。で、他にの防弾アイテムは無いのかな?」
ポンセ「姉妹品として、防弾シークレットシューズ――上げ底の部分が防弾になっていて誰にも気づかれずに身長が7センチアップするやつ――がある。という事でそいつも一応渡しておく」
俺「Thank You……と言っておこう」
ポンセ「幸運を祈る。マガジンラック」
俺「グッドラックな」
ポンセ「そう、それだ」
ポンセは指をパチンと鳴らして去って行った。
さてと、これにて全ての準備は完了した。明日は…………
俺「なるべく目立たないよう物陰にこっそり隠れてやり過ごすとしよう」
〜FiN〜。