
相変わらずの猛暑日。すっかり関東の新名所となった

東京スカイツリーの下、必死の形相で木魚をポクポクポンと叩き続けている独りのお坊さんが居た。
その額からは滝のような汗が流れ落ちている。
それでも、お坊さんは木魚を叩く手を休めようとはしない。
何故なら彼は、自分が叩く、木魚のポクポクポンと云う音がこの巨大な

東京スカイツリーを支えていると思っていたからだ。
もし自分が木魚を叩くのを止めてしまえば、その瞬間、

東京スカイツリーは倒れてしまう…頑なにそう信じ込んでいたのである。
しかし…
そのお坊さんの話はどうでも良い。
私が言いたいのは全く別の事なのである。
問題は、そのお坊さんが叩き続けている木魚だ。
その木魚はW県の人里離れた深い山奥の“御神域”とされている森から特別に切り出された物であったのだが、
実はその木魚を作った木工職人は自分の事を、伝説のヴァイオリン職人ストラディバリウスの生まれ変わりだと信じていた。
つまり彼は、自分ではヴァイオリンを作っているつもりで、ひたすら木魚を作り続けていたのである。
だが…
その木工職人の話はどうでも良い。
私が言いたいのは、そこでは無いのだ。
問題は、その木魚を買い付けている女性バイヤーにある。
実は彼女は十年前まで、海外で不法に仕入れたホッチキスの針を木魚の中に隠して国内に持ち込む【木魚密輸団】のリーダーで、事情通の話によると今までに彼女が国内に持ち込んだホッチキスの針は数十億本にも及ぶという。
しかし十年前、子供が産まれたのを機に密輸団を解散。その後、彼女は木魚業界随一の目利きとして、その名を馳せている。
木魚を木魚として正しく世の中に送り出す事こそが、これまで不当に扱ってきた木魚に対する罪滅ぼしだと彼女は信じていたのだ。
因みに彼女は、自分が密輸していた事に対する罪の意識は全く無いようであった。
が…
その女性バイヤーも木魚密輸団も、実はどうでも良い。
私が言いたいのは、また別の事なのだ。
問題は、女性バイヤーが密輸業を引退する引き金となった彼女の一人息子にある。
小学四年生の彼は、自分の母親が木魚と只ならぬ関係にあるらしい事に最近薄々感づき始めていた。
しかし彼は、それに関して母親に問い質すような事はしない。
何故なら、自分が生まれる前の母親には“一人の女としての人生”があり、それに対してとやかく云う権利は自分には無いと考えていたからだ。彼はとても利発な少年なのだ。
その利発さは、周囲の大人達も『彼は将来、立派な

理髪店のオヤジになるに違いない』と太鼓判を押す程であった。
真面目で利発な彼は、

朝、誰よりも早く学校に着く。

まだ誰もいない清々しい早朝の教室に入ると彼は、一番後ろの列の窓際の席に腰を下ろし、鞄から教科書を出して広げ、今日の授業の予習を始める。
そうこうしている内に次々と学友達が教室に入ってくるのだが、その学友の一人である【田中中田】(たなか・ちゅうた)君が毎朝必ず、彼に近づいて来てこう言うのだ。



『おい‥そこ、俺の席なんだけど』
そう…最後列の窓際の席、そこは本当は田中君の席なのである。
言われて少年もハッと自分の間違いに気づいて謝る。
『ゴメンだよ』
ところが、翌朝になると少年はまた、最後列の窓際の席に座ってしまう。


早朝、教室に入ると、彼はどうしてもそこが自分の席だと思い込んでしまうのであった。
しかし…
その問題の席も田中君も、はっきり言ってどうでも良い。
私が言いたいのは、それとはまた別の部分にある。
問題は、彼らの教室に掛かっている黒板だ。

実は、その黒板にはちょっとした噂があった。
何でも明治時代の初期、この小学校の創立時の教師であり、最初にこの教室の教壇に立った【

一二三四五六】(ひふみ・しごろう)先生が、黒板の裏の壁に土葬されていると云うのだ。
教育への情熱と子供達への愛情に溢れる

一二三先生は、その遺言で[自分が亡くなったらば、是非ともその体を黒板の裏の壁に埋葬して欲しい。私はそこから生徒達を永遠に見守ろう。人はいつか死ぬ。しかし、死なないものもあると私は信じている。板垣死すとも自由は死せず。一二三死すとも教育は死せず。スカッと爽やかコカ・コーラ

]‥そう語ったそうだ。
だが…
そんな都市伝説は全く以てどうでも良い。
問題は、その

一二三先生の息子であり


関東ローム層大学哲学科の名誉教授にして私の恩師でもある

三二一・一二三教授(サニー・ひふみ)にある。
実は今、その

サニー教授は私のすぐ目の前に居るのだ。

サニー教授はいつも背広の胸ポケットにタマネギを一つ入れていた。
私はその理由が知りたかった。
もちろん、今までに何度も聞いてみた。
最初に聞いた時、教授は『初詣でタマネギ神社に行った時に買った御守りだよ』と言った。
当然、私は冗談だと思った。
それで、もう一度改めて聞いたところ、今度は『タマネギに見えるけど、これ本当は新しい

レアアースなんだ』と言った。
その後も聞く度に別の答えが返ってきた。
私は真実が聞きたかった。
それで今日、

講義の為に大学に来ていた教授を捕まえ、今日こそは本当の事を聞き出してやろうと迫ったのであった。
「教授、そろそろ本当の事を聞かせて貰えませんか?」
すると教授は胸ポケットからタマネギを取り出して言った。

教授『君、いま私が手に持っている物は何かね?』
タマネギです‥私は答えた。
教授は私の答えに頷きながら、持っているタマネギの皮を一枚剥いた。

教授『それならば、これは何かね?』
私は躊躇なく答えた。
やはりそれもタマネギです。
教授は更にタマネギの皮を剥いて問う。

『さすればこれは?』
それもタマネギです。
教授はニヤリと笑うとタマネギの皮を次から次へと剥き始め、ついには全ての皮を剥き捨ててしまった。
教授の手のひらには、もう何も残されてはいない。

教授『では聞こう。いま私が手にしている物は何かね?‥あ、空気とか言うのは無しネ♪』
私は正直に答えた。
そこには何もありません。

教授『本当にそうかな?』
どうも良く判らない。

教授『君は最初のタマネギの姿を見て[これはタマネギだ]と言った』
はい。

教授『そして、皮を一枚剥いた物を見て[それもタマネギだ]と言った。更に一枚剥いた物をも[タマネギだ]と言ったね』
言いました。

教授『でも、全ての皮を剥いたタマネギを見た時[それはタマネギではない]と言った』
そう思ったからそう言ったのです。

教授『しかしね…全ての皮が地面に捨てられた今ここにこそ、タマネギの本質があるとは思わないか?』
どうにも…教授の話は私には理解不能であった。

教授『君がタマネギだと思っているのは本当はタマネギの皮に過ぎないのだ』
ここで教授は私の方にグッと一歩足を踏み出し、顔を近づけて来た。
こんなにも間近で教授の顔を見るのは初めてだ。

教授『君はタマネギの皮をタマネギだと言った。その下の皮もタマネギだと言った。そしてまた更にその下の皮もタマネギだと…君は[真実を知りたい]と言ったが、真実なんて物は所詮、このタマネギの皮に過ぎないのではないかな?』
弁舌に熱が入って来たのか、教授は更に私に近づいた。
…うっ

『人間は真実を求めてタマネギの皮を剥いて行く。しかし、真実と云う物は全ての皮を剥き終えたその先にあるのだ。物事の本質は、目に見える形の中には無い。だけれども人は、自分にとって都合の良い姿が表面に現れてくるとタマネギの皮を剥くのを止めてしまう。君が云う真実など所詮“その時に君が納得出来る物事の姿の一つ”に過ぎないのだ』
…ぐっ
さすがは

サニー教授である。

哲学科の名誉教授に相応しい訳の判らない話っぷりと云えよう。
しかし…
教授の判るような判らないような哲学的談義など、実はどうでも良いのである。
私が声を大にして言いたいのは、また別のところなのだ。
問題は、件の教授の足にある。
今ここに私は言おう!!
断固と!!はっきりと!!
教授…
「さっきからずっと‥貴方の足が私の足を踏んづけております!お願いですから早く足をどけて下さい!



」
随分と回り道をしてしまったが、つまりは私が言いたかったのはその一言なのである。
それが、今の私に見えるタマネギの皮。
その後、

教授の口から胸ポケットのタマネギにまつわる

悲しくも美しい真実

を聞かされる事になるのだが…それさえもまた、教授の目に映ったタマネギの皮の一枚に過ぎないのだろう。
そして、正直、そんな話はもはや私にとってどうでも良いのである。
その

悲しくも美しい物語を今ここで話すつもりは私にはない。
何故なら、私が言いたかった事は、もう既に言い終えたのだから…。
〜

終わり名古屋〜。
 相変わらずの猛暑日。すっかり関東の新名所となった
相変わらずの猛暑日。すっかり関東の新名所となった 東京スカイツリーの下、必死の形相で木魚をポクポクポンと叩き続けている独りのお坊さんが居た。
東京スカイツリーの下、必死の形相で木魚をポクポクポンと叩き続けている独りのお坊さんが居た。 東京スカイツリーを支えていると思っていたからだ。
東京スカイツリーを支えていると思っていたからだ。 東京スカイツリーは倒れてしまう…頑なにそう信じ込んでいたのである。
東京スカイツリーは倒れてしまう…頑なにそう信じ込んでいたのである。 理髪店のオヤジになるに違いない』と太鼓判を押す程であった。
理髪店のオヤジになるに違いない』と太鼓判を押す程であった。 朝、誰よりも早く学校に着く。
朝、誰よりも早く学校に着く。 まだ誰もいない清々しい早朝の教室に入ると彼は、一番後ろの列の窓際の席に腰を下ろし、鞄から教科書を出して広げ、今日の授業の予習を始める。
まだ誰もいない清々しい早朝の教室に入ると彼は、一番後ろの列の窓際の席に腰を下ろし、鞄から教科書を出して広げ、今日の授業の予習を始める。

 『おい‥そこ、俺の席なんだけど』
『おい‥そこ、俺の席なんだけど』
 早朝、教室に入ると、彼はどうしてもそこが自分の席だと思い込んでしまうのであった。
早朝、教室に入ると、彼はどうしてもそこが自分の席だと思い込んでしまうのであった。 実は、その黒板にはちょっとした噂があった。
実は、その黒板にはちょっとした噂があった。 一二三四五六】(ひふみ・しごろう)先生が、黒板の裏の壁に土葬されていると云うのだ。
一二三四五六】(ひふみ・しごろう)先生が、黒板の裏の壁に土葬されていると云うのだ。 ]‥そう語ったそうだ。
]‥そう語ったそうだ。
 レアアースなんだ』と言った。
レアアースなんだ』と言った。
 終わり名古屋〜。
終わり名古屋〜。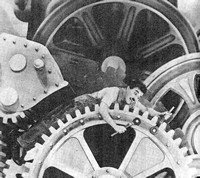
なんと可愛いらしいのでしょう
しかも、すかさずそれを
それにしても‥
で、前から思っていたのですけど…
あ、それはまた後ほど
変換欄に何故か
「タマネギ仙人」と
話がそれてしまいました
タマネギのようにめくるめくオムニバス形式の話の展開
最後に辿り着くのは…
う〜んマンダム
これ、オフニバス
シーン毎に監督をかえたりしたら面白いかも
最後の詰めは押井守辺りにやってもらいたいです
まあ、
で‥ タマネギの皮は‥あんまり深く考え無い方がいいと思う
こんな 哲学的と云うか形而上学的な事 真面目に突き詰めていったら かなりの確率で 頭が爆発すると思うから
それよりも
オチはね‥ 思考の遠近感を狂わせる為にわざと 哲学的な望遠視点から 近すぎるマクロ視点に 一気にズームダウンさせてみたって訳さ
尾張名古屋は城でもつっ
意味は判らないっ
すごいねっ!
トキノっち
いつもながら、脱帽ですっ
スカイツリーのポクポクお坊さん かわいいっ
ツボだぉっ
+.(人´Д`*).+゜.
利発で理髪店もツボっ
うぉっ!人柱って思ったんだけど…
亡くなってても人柱なのかしらっ?
でも、イヤだっ
黒板の後ろからの生徒に対する温かい眼差しっ
にやけていたりしたら、これまた怖いどっ
たまねぎの皮ねっ
なるほどっ…
なるほどっ…
…
…
↑ほらっ、難しくてフリーズしちゃったぉっ
でも、ほんと、今はこれで良いと思っていても…
追求すれば、もっと もっと 色んなコト見えてくるのかもねっ
満足しちゃったトキが終わりなのかもっ
でっ、でっ、オチがぁ〜
たまねぎで、真剣に考えていたから
余計 ずっこけたよっ
さすがさすが
ポーの
よく知ってるなあ
いや実は、この部分書いた時 自分でもポーの
それにしても‥
言われてみると 各場面に
実はね…
これ…
プラトンの洞窟 は
と云うか…
今ごろ
やっぱり…
教授の胸ポケットのタマネギの謎を知りたい…この
お坊さんの、荒唐無稽に見えるかもしれないけれど
人の人生を詮索して困らせない
誰もいない
一二三はいつか死ぬ
‥っておまぃはポーの
本当のことを
この世は全てが移ろいゆく
プラトンの
自分は、影絵の世界で
時を越えても
すっかり返事が遅くなってしまいました(泣)p(´⌒`q)
なんか最近 どうにも目が痛くて…などと云う泣きは良いとして…
確かに 場面も人物もくるくる変わるので
土葬は(笑)…
壁に埋める事を土葬と云うのはどうかとも思ったのだけれども…まあ、壁土と云う言葉もある事だし、と(笑)(≧∇≦)
どうにもこの季節は線香臭い感じに(笑)(‘o‘)ノ
ホラーになるかと思いきや、まるで仏教の「契仲造車」のような深いお話が。
タマネギの刺激臭ではなく、お線香の香りが漂う・・・ような結末になりましたですね(笑)。
紆余曲折を経て、冒頭のお坊さんとリンクする結末(私的に)・・・さすが+†+時をかける伯爵+†+です。
いえいえ… とてもとても彼には及びませんが…嬉しいです
確かに
この話は
下手すると 永遠に話が転がり続けると云う恐ろしい事態に…
良かったあ☆
( ~っ~)/
いやはや…そう言って貰えると、
なんとか この調子をキープして……行ければ良いのですけど(笑)(^w^)
相変わらずの暑い日々が続きますが…
ああ なんか
そうです
気を
気合いを入れ過ぎると腹筋がつる場合があるのでご注意を
いやいや本当にそうですよね〜
うーん 難しい
大丈夫です
私もいま 哲学と言われて思い出すの 同じく土屋先生ですから
目に見える物 見えない物
はっきり言って難しいです
ああ
新民謡
微かに記憶に引っ掛かる物が
うう…
どうも はっきりと思い出せないのだけど… えっと…
さすが
お話がクルクル変わりにゃがらめためたオッカチィれちゅニャリン
トキノ伯爵
本当にいちゅもお見事にゃ文章力にコハルわぁ
トキノさん
華麗なる完全復活ですね!
楽しかったぁ
(*^^*)
トキノさんの頭の中
MRIで見てみたいです
…あ、画像は読めないですけどね
(≧∇≦)
わたしもサニー先生の教えをモグモグ胸に秘めムシャムシャ
あ、その野菜とって
えーとタンデンに力を貯めてコハァでしたっけ千葉(関根)先生
スカイツリー
見える巨塔カラ…
皮をムキ続けたら
無に
無に
何も無いところカラ
全ては
始まるのだ
ブラボー
トキノヤ長介サン
そのとおりです(^w^)
トキノさん
ありがとうございます
見えることばかりに
とらわれ夢中になって
毎日を過ごしがちな
わたしには
こうしてお話をして
下さるひとさえ
ほとんどいないんです
見えるものが
消えたとき気づくことは
悲しみや喪失感が
どーんと襲ってくる
ことが多いのに(;_;)
どうしてすぐ
忘れてしまうのでしょう
哲学の先生といえば
土屋先生しか
頭にすぐに浮かばない
わたしですから
仕方ないですかね
(^。^;)
最近の娘の生活は
さほど以前とは
変わらないのですが
あのこもわたしも
時間をかけて
見えるだけの世界とは
少し距離のある世界で
お互いをみつめることが
出来始めてきたのかも
とか思います
が
安心などはいまだ
できないのが
正直なところです(笑)
いや 私の言いたいのは そんなことではない
玉ねぎ…
むいてもむいても芯がない
だから『新民謡』
と いう漫才があったわねぇ