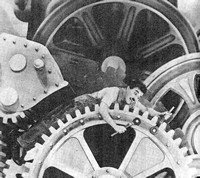話題:突発的文章・物語・詩
古びた石の塀だけが、遺跡のように、或いは何かを暗示するかのように、ポツンと取り残されている場所があった。十月の夕暮れ、陽はすっかり西に傾いている。黄昏から闇へと移行する日没寸前の世界。塀の向こう側、母屋が在ったであろう地面は既に我が物顔で蔓延(はびこ)るペンペン草で覆われており、家屋が失われて幾久しい事を暗黙の内に語っていた。其所に在ったのがどのような家であったのか、記憶を辿ってみたがまるで思い出せない。普段は殆ど通らぬ小路であるので仕方ないと云えばそうなのだろう。
夕焼けに塀だけが浮かび上がる空間風景はどこか寂しく同時に奇妙であるが、その異質さに輪をかけているのが、塀に描かれた〈海の絵〉であった。但し、絵と云ってもそれは限りなく落書きに近いものである。と云って、近年、都市部で見かけるような〈アートとしての落書き〉とも違うように思える。もし、これがアートであるならば、町中にある道路標識などは至高の芸術作品となり、まとめて美術館に寄贈しなければならないだろう。
誰が描いたとも知れぬ塀の落書き。覚束ない〈海の絵〉。砂浜の先にはどう見ても水平ではない水平線がひかれ、まぱらな雲、好意的に見ればカモメに見えなくもない小さな飛行物体、そのようなものたちが塀というカンパスの上、妙にくすぐったいバランスで描かれていた。
いったい、何時、誰が、何を思って、描いたのだろう。そ取り留めもなくそんな事を考えながら塀の落書き絵を見つめていると、ポッ、塀の中央より少し下辺りに突然、輝くような茜色の小さな円が現れたのであった。と、それが合図であるかのように風景が暗くなり、瞬く間に空に宇宙が現れた。輝く茜色の小さな火球は塀の風景の中を徐々に下降したかと思うと、やがて、〈海の絵〉の水平線に差しかかる辺りで深いコバルトの青に溶け込むように消えていった。その光景は紛れもなく海の彼方に沈みゆく太陽そのもので、成程々々、何故ここに海の絵が描かれたのか、その秘密をこの瞬間に見たような気がしたのであった。私と同じように、塀の中に突然現れた火球を見た誰かが、それを太陽に見立て、ちょうどその沈みゆく辺りに海の水平線を描いたのであろう。火球が現れてから消える迄、日没前の僅か一分間にのみ解き明かされる〈海の絵〉の秘密。古びた塀の幻燈。
実際に此所から西に数㎞離れた所には海があり、太陽はその彼方に沈んでゆく。塀に現れた茜色の小さな円の光源が、その沈みゆく太陽であるのは疑いようがない。地平ギリギリの低い傾斜角から太陽の放つ、日の終わりの鋭い残光が、砂浜や防砂林、県道、公園や神社、民家など中途に在る様々な遮蔽物を通過して濾過され、この場所(塀)にたどり着いた時にはピンポン玉とテニスボールの中間くらいの火球となった。いみじくもその形と輝きは小さな太陽そのものであり、それは奇跡的な相似と云えた。
何故この場所に塀だけが残されたのか。それは、無断で土地に侵入するのを防ぐ為の心理的な抑止力になると管理者が判断したと云う極めて現実的な理由によるものかも知れないし、或いは、人知では計り知れない神秘的な力が其所に働いているせいかも知れない。
かえすがえすも残念なのは絵の出来映えで、描いたのが誰であるにせよ、もう少し上手く描けなかったのだろうかと思ってしまう。悪く云えば下手くそで、良く云えば下手っぴ。けれども、その、完成されていないタドタドしさ、至らなさ故にある種の情感がそこに生まれているようにも思える。明解な答を持たない芸術はやはりムツカシイ。塀の火球に海に沈む夕陽を見つけた感度(センス)の高さと、実力の低さ(絵心の無さ)。その埋めるに埋まらぬ距離感が何とも哀しく、それが秋の日暮れの寂しさと不思議に共鳴しあっていた。
――かつて此の場所には年老いた犬と老人が住んでいた……としたら。彼らは毎日夕暮れの海を散歩し、水平線に沈む太陽を二人で眺めていた……としたら。しかし、時は無常に進み、季節は移りゆく。足の弱った老犬は海まで歩く事が難しくなり、老人もまた同様であった。それでも二人は夕暮れに家の前の僅かな距離を散歩した。そんな或る日、老人は塀の上に小さな火球が現れるのを見つけた。老人にとってそれは落陽そのものであった。そして老人は何の技術も経験も無いまま、塀に〈海の絵〉を描いた。もう海へは行けない老犬と自分の為に、海を、そして海の彼方に沈む太陽を、一枚の古びた塀に閉じ込めた。それは日没前の僅か一分間のみ現れる、年老いた犬と老人だけが知る秘密の風景。やがて二人は共に旅立ち、秘密だけが此所に残された……としたら。
……それを、塀に描かれた〈海の絵〉が語る秘密の物語とするのは、いささか感傷的に過ぎるだろうか――
陽の落ちてしまった海は、燃え尽きてしまった線香花火のように哀しい。
秋にはぐれた蜻蛉が一羽、塀の中の海へと消えていった。いったい、何処までが実際の風景で、何処からが心象の風景であったのか。見つめる私もまた、十月の落陽を彷徨う名もなき一羽の蜻蛉であった。深まりゆく秋の面差し、夜風に遠く金木犀が薫っている。
~おしまい~。