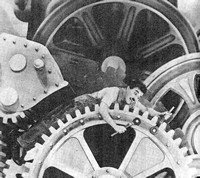話題:SS
どんな景色が見えるのだろう。そんな期待を胸に僕は展望鏡の接眼部に両目をあて中を覗き込んだ。
ところが……
そこには漆黒の闇が広がるばかりで他には何も見えない。目を離して、もう一度、ランプの色を確認する。ちゃんと緑になっている。が、再度覗き込んでも風景はまったく見えなかった。(これはおかしい。機械の故障だろうか)。そう思った時だった。
『ねぇ、君…』
背後で声がした。踏み台に載ったまま振り向くと、すぐ後ろに白い服を着た男が立っている。いったい、何時からそこにいたのだろう。近づいてくる足音も気配もまるで感じられなかった。しかし、男は疑いもなく厳然とそこに立っていた。年の頃はよく判らない。スラッとした体躯で背は高かったように思う。
もっとも、その辺は幾らか曖昧なところがある。如何せん古い記憶の中の出来事だし、何と言っても当事の僕はまだ幼かった。ただ、男の着ている服の眩いばかりの白さだけは今も判然(はっきり)と脳裡に焼きついている。白の背広に白いシャツ、白のスラックス、靴まで白い。その上、白い帽子まで被っている。そのどれもが、汚れ一つない輝くような純白だ。
男は涼しげな表情で言った。
『目じゃない。鼻だよ』
意味が判らずにポカンとしていると、男は同じ内容の事を別の言葉を使って言い直した。
『いま、君が目をあてていた箇所(とこら)には鼻をあてるんだ。それが、この機械の正式な使い方なのさ』
言い直されてもまだ意味が判らない。それでも、言われるままに僕は展望鏡の――本来、どう考えても目をあてるべき――接眼部に両鼻をあててみた。
しかし、これがやはり何も起こらない。からかわれたのか、と一瞬思った。
でも、そうではなかった。
『ああ、申し訳ない。どうやら、私が話しかけたせいでコインの有効時間が切れてしまったようだ』
見れば、いつの間にかコインランプの表示色が赤に戻っている。僕が財布から次の十円玉を取り出そうとすると、男の手が静かに延びてきてそれを制した。そして、僕の手に十円玉を何枚か握らせた。それは展望鏡と同じく新品同様にピカピカと輝いていた。その十円玉を男が何時どこから取り出したのか、僕にはまるで見えなかった。それは熟練の手品師の技を見ているようだった。
『このコインは君の邪魔をしてしまったお詫びだ。さあ、もう一度試してごらん』
僕は言われた通り十円玉をコインボックスに入れた。ランプが緑に変わる。そして、展望鏡の接眼部に恐る恐る鼻をあてた……。
すると、どうだろう。僕の鼻孔いっぱいに何とも言えず香しい(かぐわしい)花の芳香がたちまち広がったのだった。この香りには覚えがある。見覚えではなく聞き覚えでもない。嗅ぎ覚え。それはラベンダーの芳香に違いなかった。
展望鏡のレンズの遥か向こうには広大なラベンダー畑が広がっている。それは、つまり……。
『そういう事。これは視覚ではなく嗅覚を望遠する、そういう装置なんだ』
幼い身にも、それが不思議な話だというのは判る。
『遠くにある香りを拡大して集積させる望遠鏡。でも、実を言えば、この装置はまだ実験段階の物なんだ』
男は意外と饒舌で、話はもう少し続いたが、それは当時の僕にはあまりに難しすぎる内容だった。
知識や理解を超えた話は遠い異国の言葉のように右の耳から左の耳へと吹き抜ける。あとに残るのは風に吹かれた感覚だけだ。この時、僕は確かに遠い異国の風をこの身に感じていた。それは僕の知らない世界に吹く風だ。
『じゃあ今度は…香りを嗅ぎながら目を閉じてみて』
目を瞑って鼻をあてる。再びラベンダーの芳香が僕の鼻孔を満たしてゆく。変化は間もなく訪れた。目を閉じた漆黒の世界にスッと一条の光が差し込んだかと思うと、夜が一瞬のうちに昼に変わるように、暗闇の世界は突如として、風そよぎ光あふれる花畑の風景へと変貌を遂げたのだ。
それはとてもリアルな光景で、僕は現実のラベンダー畑の中に立っているような感覚に陷っていた。現実のまぶたはしっかりと閉じられている。しかし、風景はこれ以上ないぐらい鮮明な映像として脳内スクリーンに映し出されていた。
どれぐらい、そうして花畑の中で立ち尽くしていただろう。やがて世界は、部屋の電気を消すように、一瞬でまた元の暗闇に戻ってしまった。
目をあけた僕は、たったいま自分が目にしたものを男に伝えようと背後を振り返った。
が、男の姿は跡形もなく消えていた。そして、その消失と入れ替わるように屋上のあちこちに人の姿が現れていた。幼い子供をつれた母親と父親。仲の良さそうなお年寄りの夫婦。ネクタイを緩めてベンチの上で足を投げ出している背広姿のサラリーマン。それは、百貨店の屋上によくある日常の風景そのものだった。
《続きは追記からどうぞ》