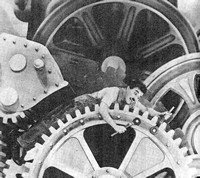ある会社の応接室。一応は商社であるが、築の古い賃貸ビルに間借りしている時点で大手でない事は判る。その一室に、二人の男性が向かい合って座っていた。一人はカジュアルな格好の中年男性で、取引先の会社の人間もしくは一般の顧客であるらしい。もう片方は当然会社側の人間―いわゆる商社マンであるが、二十歳そこそこで背広姿が全く板についていない。見るからに頼りない。新入社員か、それに準ずる存在であろう。
二人は商取引の話をしているようだった。が、それは順調さを欠いているように見える。顧客の男は明らかに苛立っていた。それに対し、若い商社マンはただオロオロとするばかり。
『君の話しは先刻からどうも要領を得ないね』。『はぁ…担当の者が急な出張で不在でして…』。どうやらそういう事らしい。『こちらとして急いでるのだがね』。『…ですよね』。『このまま貴方と話しを進めても大丈夫なのだろうね』。『さあ…どうでしょうか』。
頼りない答えのオンパレードである。顧客の男性も流石に、この相手はラチが開かないと思ったのだろう。『悪いけど、誰か別の人を呼んで貰えないかな』。『えーと…誰を呼べば良いのでしょう』。打ってもまるで響かない、低反発マットレスのような男である。『もう誰でも良いから、とにかく上の人間と代わってくれー』。それはもはや悲鳴に近かった。『判りました、では一応呼びに行ってみますけど、もしかしたら誰もいないかも…』。とことん頼りない台詞を残し、若き商社マンは部屋から出て行った。
『一応、呼んで来ましたけど…』。間もなく戻って来た彼の横から一人のお爺ちゃんが顔を出す。『あのぅ…わしをお呼びだそうじゃが…何か御用で?』。寝間着姿のお爺ちゃん。とても商社マンとは思えない。顧客の男性が訊ねる。『貴方が…上の方?』。お爺ちゃんが答える。
『はぁ…確かにわしは、“上の階”に住んどる、このビルの大家じゃが…』。
こういう場合は、この台詞しかないだろう。顧客の男性は思っていた。
『だめだ、こりゃ』。
〜〜おしまい〜〜。