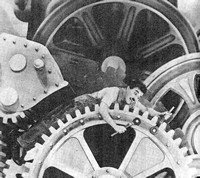話題:連載創作小説
[演奏会の開始は夕方の六時ごろです]
そんな手書きの貼り紙が店内のところゞに貼られいる。“午後六時”ではなく“夕方の六時ごろ”というのが如何にもマスターらしい。彼女はそう思っていた。
その“夕方の六時ごろ”には、時間にしてまだ三十分ほど余裕がある。その間彼女は、今夜の共演者であるプレイエルピアノの傍らの席に座り、この二ヶ月に起きた事をぼんやりと考えながら過ごしていた。
名曲喫茶【平均律】…雨の降るテラス席…憂いの影を持つ美しい青年…それが全ての始まりだった。やがて、青年の姿は失われ、彼女は【平均律】へと足を踏み入れた。そこで交わされたマスターとの会話…その何気ない一つの会話から彼女はこの名曲喫茶に通う事となり、一台の古いピアノと巡り逢う…。
1837年製のプレイエル。
思えば、それは不思議なピアノだった。彼女は傍らのプレイエルに視線を向けた。店内にはバダジェフスカの《乙女の祈り》が静かに流れている。
普通――プレイエルを見つめながら再び彼女は考え始めていた――ピアノの寿命というのはせいぜい百年がいいところだ。それ以上の年月を持たせる為には神経をすり減らすぐらい入念な手入れと保管とが必要になる。
このプレイエルは作られてから、もう百八十年近くになる。そして見る限りにおいては、定期的に入念な手入れがされた気配もなく、また、博物館のような行き届いた設備環境で保管されていたとも思えない。にも関わらず、その伸びやかな美しい音色をまるで失なっていないというのは彼女にはとても考えられない事だった。事実、彼女が最初にプレイエルと対面した時、この古いピアノは鍵盤も屋根板の隙間もフットペダルも綿埃をかぶっていて、調律もまったくされていなかった。
確かに、途中でマスターの叔父による大幅な復元修理が行われた事は知っている。孤高のマエストロと云って良いマスターの叔父の楽器職人としての腕が相当高かったのも事実だろう。しかし、それを考慮に入れたとしても、この古いプレイエルピアノから立ち昇る天使のような澄みやかな歌声は、現実の領域を超えて存在しているように彼女には思えた。
その不思議な力は何処からやって来るのか?その源泉はいったい何なのか?
実は、それについて彼女は既に自分なりの答えを持っていた。
「この1837年製のプレイエルはショパン本人が実際に弾いていた物に違いない」。それが彼女の出した答えだった。
確かにそれは空想と云えば空想である。しかし、年代と場所から云えば、その可能性は十分にある。ショパンが仏プレイエル社のピアノに特別な思い入れを持っていた事は、ショパンを弾く人間なら知らぬ者はない。そして、マスターの叔父が修理を依頼されたのもフランスだ。もしも彼に修理を依頼してきた人物が旧いフランスの貴族であるならば、それが本物のショパンのピアノである可能性はいよいよ高くなる。ショパンの生きていた時代、音楽家と宮廷や貴族とは切っても切り離せない密接な関係にあったのだ。
彼女は殆んどそれを確信していた。ただ、それを検証する事はまず不可能である。もしかすると、このプレイエルには今でもショパンの指紋が残されているかも知れないが、そもそも、ショパンの指紋を知る者など誰ひとりとしていない。十九世紀半ばのヨーロッパには指紋登録システムなど存在しないのだ。
このピアノを本物のショパンが弾いていた事を証明するのは不可能だ。でも、それでいい。彼女は、その空想めいた秘密を自分ひとりの胸の中にしまっておく事にした。
《続きは追記からどうぞ♪》