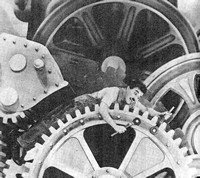話題:連載創作小説
その日は朝から雨が降っていた。
彼女は、焼香する場所から少し離れ、木々の立ち並ぶ屋外に傘を開いて立っていた。
黒い服に身を包んだ人たちは誰もが伏し目がちで、今日という一日が哀しい日である事を教えていた。身を寄せてひそひそと会話を交わす集団もあれば、彼女のように独りで立っている者もいた。
彼女が名曲喫茶【平均律】で初めてプレイエルのピアノを弾いた日の夜。帰宅した彼女は留守番電話に一件のメッセージが残されているのを見つけた。それは、古い知り合いからのものだった。
もう何年も交流のない人物からの突然の連絡に、彼女は少し嫌な予感がした。そして、その予感は当たっていた。
それは、彼女が三歳から十五歳まで師事していたピアノの先生が亡くなったという知らせだった。
古い知り合いは、葬儀の日時と会場の場所を急ぎ口調で告げ「逢いに来てくれると先生もお喜びになると思います」とメッセージの最後を結んだ。
先生とは、最後にお会いしたのが何時だったのか忘れるくらい縁が遠くなっている。そんな自分が果たして葬儀などに出て良いものか、彼女は少し迷った。
しかし、先生には随分とお世話になった事もまた変えようのない事実だった。彼女にピアノの弾き方のイロハを教えてくれたのは先生で、そういう意味でも彼女の人生にとって最も思い出深い人間の一人である事は間違いない。
やはり、先生には最後にきちんと挨拶をして感謝の言葉を一言でも述べておきたい。こうして彼女は、亡き恩師の葬儀に参列する事を決めたのだった。
棺の中に眠るかつての恩師は、安らかな顔をしていた。ロマンスグレーの長い髪は艶やかで美しく、頬はうっすらと紅色に染まっている。その姿は、彼女の知る頃から少しも歳をとっていないように見えた。
彼女は恩師の亡骸に「ありがとうございました」と小さく声をかけ、その場を離れた。そして、そこから少し離れた木々の下に立ち、静かに葬送のセレモニーを見つめ続けた。
冬の日の葬送は少し哀しい。
雨の日の葬送は少し切ない。
けれども、そこには何処か胸に響くような美しさがあるように彼女には映っていた。
もしかするとそれは、人間や人生と云ったものが、その死や終焉をも含めて美しい存在である、という事の一つの証明なのかも知れない。彼女は何となくそんな事を思った。
恩師の葬儀は、生涯ピアノ教師だった人間に相応しく音楽葬の形をとっていた。
クラシックの有名な曲がピアノ曲を中心として、冬の空に流れ続けている。それは、花の咲かない季節に誰かから贈り届けられた音楽の花束であるように彼女には思えていた。
ラヴェルの《水の戯れ》が終わり、次の曲が流れ始める。その曲に、彼女の体が反射的にピクンと小さく反応した。
それは彼女がピアノを習い始めるきっかけとなった曲だった。
幼き日に偶然その曲を耳にした彼女は、家にあった玩具のピアノの鍵盤を叩き始めたらしい。彼女自身はよく覚えていないが、彼女の母親はそう言っていた。そして、夢中で玩具のピアノを弾き続ける彼女の姿を見た母親は、父と相談して彼女にピアノを習わせる事を決めた。その時、近所でピアノ教室を開いていたのが棺の中の恩師で、彼女はその教室に通うようになった……。
つい昨日の出来事のように彼女はそれを思い出していた。
《続きは追記からどうぞ♪》