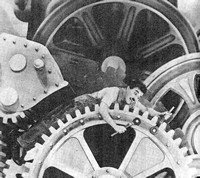話題:連載創作小説
いざピアノを弾き始めようとして、彼女はふと今の今まで横にいたはずのマスターの姿が消えている事に気づいた。……どうしたのだろう?そう思っていると、それまで店内に流れていたラフマニノフの曲がピタリと止んだ。なるほど、そういう事か。演奏の邪魔にならないよう、マスターはレコードの針を戻しに一旦この場を離れたに違いない。飄々としている割りに細やかなところに気のまわる人だ。
マスターが戻ってくると彼女はその配慮に対し短く感謝の言葉を述べた。この、ちょっとした間(ま)のお陰で、それまで張りつめていた場の空気が少し緩み、彼女の緊張も幾分和らいでいた。
彼女は自分の体に体温が戻ってくるのを感じながら、鍵盤の上の虚空に空気を柔らかく包み込むように手のひらを置いた。そして静かにゆっくり呼吸を整え始める。それは彼女がピアノを弾き始める時に必ず行う、云うなれば儀式のようなものだった。
思えばピアノにはもう七年もの間まったく触れていない。物心のついた時分から毎日何時間も弾き続けてきたピアノとは云え、七年というブランクはそう簡単には埋まらない。
彼女は少し迷った末、曲をエリック・サティの《ジュ・テ・ヴ》に決めた。軽やかな優美さを持つこの曲は、その華やかさの割に難易度はかなり低い。流石に長期のブランク明けで、リストの《超絶技巧曲集》を選ぶ自信は彼女にはなかった。
マスターと常連客たちの見守るなか、彼女はゆっくりと1837年製プレイエルの鍵盤の一つに指を下ろした。
鍵盤に触れた指先に象牙のひんやりとした感触が伝わる。その瞬間。伸びやかな歌声のような美しい音が、蜜を吸った蝶が花弁から舞い上がるように店内に響き渡った。それは、シンギングトーンと呼ばれる最高級のプレイエルに特有の音色であった。
正直、実際にこうして鍵盤に触れる迄、彼女は自分がちゃんとピアノを弾けるかどうか、全く自信がなかった。しかし、彼女の指先は彼女の心はピアノの弾き方を忘れてはいなかった。彼女の白い指先が、まるでそれ自体が意思を持つ生き物であるかのように鍵盤の上を軽やかに舞い、踊った。
そして、気づいた時には彼女は一つの音符をも違える事なく《ジュ・テ・ヴ》を完奏していたのだった。
周囲で小さな拍手が起こる。マスターも常連客たちも、初めて耳にするプレイエルの音色と彼女の見事な演奏に感嘆のため息を漏らしていた。
「いや…素晴らしかったです」
芯から感心したようなマスターの言葉に他の常連客も頷く。
彼女は少し顔を赤らめながら椅子から立ち上がると、軽く頭を下げた。その様子は如何にも、曲を無事に弾き終え、安堵している演奏者のそれであったが、彼女の内心はそれとはまた少し違う事を思っていた。
《続きは追記からどうぞ♪》