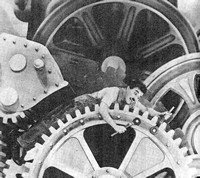話題:連載創作小説
―Unplugged short story-1―
1838年 スペイン領マジョルカ島 晩秋。
楽園の孤島と呼ばれ、いつもは暖かな陽射しの降りそそぐ地中海のこの島も、時は十月、雨季の長雨に晒される肌寒い日々が続いていた。この年の雨は特に冷たく、風光明媚で知られる風景もすっかりとその豊かな色彩を失ない、空一面を重たく覆いつくす雨雲と共に見る者に憂鬱な印象を与えていた。
マジョルカ(マヨルカ)島の中心部からかなり離れた深い山の中にヴァルデモサという名前の村がある。落ち着いた雰囲気の石畳の街路に建ち並ぶ数々の建物もやはり堅固な石造りで、それを美しい稜線を持つ山並みが取り囲んでいる。
そんな絵葉書の風景のような美しいヴァルデモサの村の小さな修道院、その一室に若い男性の姿があった。年の頃は三十くらいだろうか。繊細さを感じさせる端整な顔立ち。しかしそこには深い翳りの色が確かに見えていた。
時刻は朝。しかし、昨夜から降り続く雨のせいで、朝の光はどこか弱々しく遠慮がちに窓の硝子を蒼白く照らしていた。
部屋の扉が静かに開く音がして、艶やかな長い黒髪の女性が姿を見せた。その女性は少し心配そうな顔つきで部屋の中にいる男に声をかけた。
「…起きていて大丈夫?もう少し横になっていた方が…」
男は、あまり力強いとは云えない微笑みでそれに答えた。
「いや、今朝はいくらか体調が良いんだ。ようやくピアノも届いた事だし…」
言葉の途中で男が激しく咳き込む。普通の咳ではない。女性が慌てて男に駆け寄り背中にそっと手を置く。
見ての通り、男の体は病に蝕まれていた。病名は結核。その転地療養の為、男は温暖なマジョルカ島を訪れていた。当初は島の中心部にある【風の家】という名の貸し別荘に滞在していたが、彼が結核である事が周囲に知られると、次第に其所に居づらいようになり、街から離れた山間の修道院へとその居を移したのだった。結核は当時、伝染性を持つ不治の病として知られていた。
男の咳は程なく止まった。
「すまない…もう大丈夫」
しかし、女が心配そうな表情を崩す事はなかった。
「やっぱり、もう少し休んでいた方が…」
だが、男はそれに対して小さく首を横に振った。
《続きは追記からどうぞ♪》