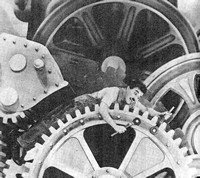話題:創作小説
忘れ物を取りに戻った放課後の教室は、窓から差し込む西日のほかには誰もいなかった。
夕焼けのオレンジと机や椅子の薄黒い影。人気の消えた六年二組は、まるで小さな世紀末のようだった。そんな教室で僕は一本のチョークを盗んだ。黒板の下に先生が置き忘れた青色の真新しいチョークだ。
最初は盗むつもりなど全くなかった。しかし、ぽつんと置かれた真新しい青色のチョークを目にした瞬間、或る一つの素敵な計画が頭の中に浮かび、気づいた時には僕はもう、青いチョークを上着のポケットにそっと忍ばせ、逃げるように黄昏の校舎を後にしていた。
計画はこういうものだ。まず、家の玄関の前の路上に立つ。そこからチョークで道に線を引き始める。そのまま出来る限り道を真っ直ぐに進んで行く。すると、道には青い粉の線が延びて行き、逆に、使われた分だけチョークは短くなって行くだろう。そういうふうにチョークで道に線を引きながら家の前からひたすら道を真っ直ぐ進んで行く。
やがて、何処かでチョークは無くなるはずだ。そして僕はチョークが完全に失われたその場所を【世界の果て】と定める事にした。一本のチョークが一つの世界を持っているとするならば、そこは紛れもなくそのチョークにとって【世界の果て】となるはずだった。それが夕暮れの教室で僕が立てた密かな計画の全貌だ。
決行は次の金曜日の午後四時と決めていた。何故なら、その日は僕の十二歳の誕生日で産まれた時刻が午後四時だからだ。誕生日に【或る一つの世界の果て】を知る。それはとても素敵な事のように思えた。
そして金曜日、僕は予定通り午後四時ちょうどに家の前から盗んだチョークを使って道に線を引き始めた。
固いクセに脆いチョークを折らないよう線を引いて行くのは意外と大変な作業だった。僕は手のひらで包み込むように深くチョークを握り、先端の数センチだけを地面に擦りつける格好で線を引いて行った。鉛筆の芯は長いほど折れやすく短いほど折れにくい。そんな理屈をチョークにも当て嵌めたわけだ。
曲がらないよう道に線を引いて行くのも思っていた以上に難しかった。普通に靴で歩いている時には気づかなかった細かな凹凸が何度も僕の行く手を阻もうとした。走っている車やバイク、自転車にも気を付ける必要があった。兎に角、道はとことん険しいものだった。
しかし【世界の果て】を知るには、それも当然だというように僕は思っていた。
そんなふうにして、僕は慎重にそして確実に、細心の注意を払いながら青いチョークで道に真っ直ぐな線を引き続けた。
幸いな事に途中で友達に出会すような事はなかった。もし、誰かと出会っていたら何て説明すれば良いのだろう。本当の事など、とても言えそうにない。
迂闊にも「この青いチョークがなくなった場所こそ【世界の果て】なんだ」などと言おうものなら、その友達が誰であれ、十中八九、こう言い返してくるだろう。「そんな馬鹿な話があるもんか」と。
そして、その瞬間、【世界の果て】は僕の中から失われる。永遠に。夢から覚めた瞬間に夢が終わってしまうように、誰かに一度でも否定されてしまえば、僕の【世界の果て】を知る計画は終わりとなる。それほど迄に、この計画は脆くデリケートなものだった。
〜続きは追記からどうぞ♪〜