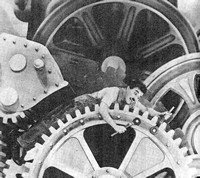話題:創作小説
あの夏、僕は小学六年生だった。
七月の初めの茹だるような暑い日曜の昼。母がこしらえたライスカレーを食べようとした僕は、ほんの僅かな隙を突かれ、逆にライスカレーに食べられてしまったのだ。
明らかな油断であった。その時たまたまつけていたテレビの画面にチラリと映ったディック・ミネの蝶ネクタイに、瞬間、気を取られていたのだ。
ダイナ♪私の恋人♪
胸に描くは♪美し姿♪
僕はその歌をライスカレーの中で聴いた。
それはつまり、僕はライスカレーに食べられながらも無事であり、同時に、ライスカレーの中には僕が個体として存在し得るだけの空間世界が広がっていた事を示していた。
そう。
ライスカレーの中には、カレー界とでも云うべき新世界が在り、それはちょうど、地上で云うところの鍾乳洞のような造形を持つ世界だったのだ。
ゴツゴツしたウコン色の地面に突如として放り出された僕は、当然の事ながら、何が起きたのかまるで理解出来ず、ただ茫然とその場にしゃがみ込んでいた。
すると、
『なんだ、お前さんも来ちゃったのかい?』
唐突に背後から声がしたので反射的に振り返ると、そこにはどこからどうみてもジャガイモにしか見えない姿があった。
私『えっと…あなたは?』
ジャガ『ジャガイモだけど』
確かに。これ以上、的を射た返答は存在しないだろう。
と、今度はそこへ、明らかにニンジンと思われる物体が近づいて来た。
ニンジン『ジャガちゃん、どうしたの?』
ジャガ『あ、いいとこに来てくれた。いやね…この子、事態が飲み込めてないらしいんだ』
ニンジン『あらまあ…それは可哀想に』
そう云うと、ニンジンは幾らか憐れみのこもった眼差しで僕を見た。
ニンジン『初めまして、こんにちわ。私、ニンジンです』
私『はぁ…どうも、初めまして…えっと…人間です』
ニンジン『あのね…』
私『はい』
ニンジン『どうやら、状況が判ってないみたいだから説明してあげるけど…』
私『あ、お願いします…』
ニンジン『あのね…とっても云いにくい事なんだけど…君、ライスカレーに食べられちゃったんだな』
私『えっ!?』
ジャガイモが横から口を挟む。
ジャガ『まあ、信じられないのも無理ゃないわな。でもさ、今となってはお前さんも俺らと同じ、立派なカレーの具ってわけだ』
此処にきて、ようやく僕は少しずつ事態が飲み込めてきた。確かに僕はライスカレーを食べていた。そこで急に目の前が真っ黄色になって、気がついたら此の鍾乳洞のような場所に投げ出されていた。以上の流れを鑑みれば、一見荒唐無稽なニンジンの話も説得力を持ってくる。
ニンジン『どうかな?ちょっとは飲み込めてきたかしら?』
極めて不条理な状況ではあるが、それ以外に答えがなさそうなのもまた事実だった。
私『ええ…ライスカレーに飲み込まれたのかも知れないって事を…飲み込みました』
ジャガ『飲み込まれたのを飲み込む、か。こりぁ、傑作だ』
笑うジャガイモに、ニンジンが少したしなめるような口調で云う。
ニンジン『笑わないの。この子にしてみればショックな事なんだから』
それはそうだ。完全に自分は“飲み込む側”だと思っていたのが、よもやの反転で“飲み込まれる側”になったのだ。
ジャガ『すまんすまん…そうだわな…俺たちは野菜だから“いつかカレーの具になる日が来るかも”って子供の頃から覚悟してるけど、人間は違うもんなあ』
知らなかった…。野菜がそんな覚悟を持って生きているなんて。
私『なんか…ごめんなさい。いつも食べるばっかりで』
ニンジン『いや、それはいいのよ。そう云うシステムなんだから。それよりも、困ったわね…』
私『えっ、何がですか?』
ニンジン『私たち、君に食べられるつもりで待ってたのよ。それが、君が具になって食べる側が居なくなっちゃった』
ニンジンの言葉に、或る恐ろしい考えが浮かぶ。
私『僕…食べられてしまうの?』
その時だった。
カレー鍾乳洞の中に濃厚な香りの風が吹いたかと思うと、何とも例えようのない姿をした者が登場したのだ。
ジャガ『あ、これはこれは…』
ニンジン『フォンドボー閣下じゃありませんか。まあ、こんなところにいらっしゃるとは珍しいこと…』
すると、フォンドボー閣下と呼ばれた男(…なのか女なのかはサッパリ判らないが…)は威厳の満ち溢れた声で云った。
閣下『うむ。何やら珍客が来ているらしいと聞いたらものでな』
そう云いながら顔を覗き込んでくる。
私『…ど、どうも…初めまして』
間近で見るフォンドボー閣下は物凄い迫力だった。全てがギュッと凝縮していて、その姿はどこか宇宙科学図鑑のブラックホールを彷彿とさせた。
閣下『うむうむ、苦しゅうないぞ。そうか…珍客と云うのは君の事であったか』
私『…はい』
普通に考えれば、どうみてもフォンドボー閣下の方が珍しい存在なのだが…ここはライスカレーの中の世界…内容物としては人間の方が珍しいのだろう。
私『それで、あの…』
閣下『ん?遠慮せず何でも尋ねるが良いぞ』
私『あの…僕も皆さんと一緒に、カレーの具として誰かに食べられてしまうのでしょうか?』
閣下『うむむむむ〜ん』
閣下は腕組みをしながら、何やら濃厚な顔つきで考え込んでいたが、やがて、こってりとした厳しさを含む口調で云った。
閣下『このままでは、そうなるかも知れん』
ニンジン『可哀想だわ』
ジャガ『急に食べられる覚悟しろっても、無理な話だわな』
私『……』
閣下『如何にも。わしなどは、エキスとして抽出された時点で九分九厘、カレーかシチューにされるであろうと覚悟を決めておるが…人間ともなれば、そうはいくまい』
ニンジン『ねぇ、閣下、私たちの力で何とかしてあげられないかしら?』
ジャガ『そうですとも!フォンドボー閣下のコクを持ってすればアイディアの一つや二つは…ねぇ』
閣下『うむ、無いでもないが…それには、まずは時間を稼がねばならん。時に、君…』
私『はい』
閣下『このライスカレーを作ったのは誰かね?』
私『お母さんです』
閣下『して、その母上は今何処へ?』
私『二階のベランダで洗濯物を干していると思います』
閣下『では、まずは母上が戻ってくるのを待つとしよう』
ニンジン『待ってどうするの?』
閣下『彼がここにいる事を何とかして母上に伝えねばならん。息子がカレーの中に溶け込んでいると判れば、誰かがこのカレーを食べるのを防いでくれるに違いあるまい』
ジャガ『流石は閣下!…でも、どうやって伝えるんで?』
閣下『大声で叫ぶ』
それは、ど真ん中へ豪速球のストレートを投げ込むような、気持ちいいくらい直球な方法だった。
ニンジン『声…届くかしら?』
閣下『骨髄の奥底から叫べば必ずや届く…わしはそう信じておる』
ジャガ『今こそ、具材の心意気をみせる時さね!』
閣下『では、君…』
私『はい』
閣下『母上が戻ってくるまで、このカレー世界の話でもしながら待つとしようではないか…』
あの夏。
僕はこうしてカレー世界の住人となったのだった…。
前編終了〜中編へ続く。