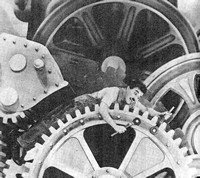話題:連載創作小説
午後七時を少し回った水島邸のリビングルーム。カーテンの締め切られた部屋の灯りが夜に浮かんでいた。端から見ればそれは、ごく一般的な家庭のささやかな夕食時の風景にしか見えないだろう。
よもや、現在この部屋で誘拐事件が…それも、極めて事情の込み入った事件が進行中だとは、誰一人、夢にも思わないに違いない。
しかし、その複雑すぎる誘拐事件も、いよいよもって終焉の時を迎えようとしていた…。
リビングの机に置かれた電話機のスピーカーから、全てをやり終えた博之の少し誇らしげな声が流れてくる。しかし二人は、得意気に話す息子に言葉を返す事はなかった。返さなかったのではなく返せなかった。言うべき言葉が見つからなかったのだ。
(ねぇ…聴いてる?)
押し黙る両親に焦れったさを隠しきれない博之の声に対し、
母親の佐智子は、「うん」と一言を返すのが精一杯だった。
すると、突然何かに気付いたように博之が(あっ!)と短く声を上げたのだった。
(あ、そうだ!)
「なに?」
ほとんど反射的に聞き返した佐智子に、博之は特に悪びれたふうもなく言った。
(門限の七時、破っちゃってゴメンナサイ。…でも、悪い人を地球から一人減らしたんだから、許してくれるよね? 来月のお小遣い減らしたりしないよね?)
その言葉はやはり、どこまでも無邪気で、恐ろしいまでに純粋無垢なものだった。
「ええ…大丈夫よ。お小遣い減らしたりなんかしないから」
佐智子は、そう答えるのがやっとだった。一方、父親の隆博は、二人の会話が耳に入っているのかいないのか、先程からずっと目の前の何もない空間を放心した様子で眺め続けていた。
(良かった…。だって、もしママとパパが犯人の味方するような事を言ったら…悲しいけど、その時は二人を“植物に変えなきゃ”ならないから…それが僕ら、“地球の意志”によって誕生した《新緑の世代》の使命だからさ)
安堵の混じる声で話す博之。しかし、その安堵が自分の親に対して力を使わずに済んだ事への安堵なのか、お小遣いが減らされなかった事への安堵なのか、それを見極めるすべを二人は持たなかった。
どれくらい前になるだろうか…博之は以前、《新緑の世代》の一人として二人に、こんな話をしていた…。
「僕ら《新緑の世代》の人間の体からは、悪い大人を呼び寄せるフェロモンのような物が出てるんだよ。もちろん、集まってくる大人全員がそうではないけど、僕らには悪い大人を嗅ぎ分ける独自の嗅覚があるからすぐに判るんだ」
この時点で佐智子と隆博は、息子は変なコミックの影響か何かで、自分が空想上の主人公になったつもりで遊んでいるに違いないと思っていた。単なる子供には有りがちな話の一つだろうと。
そこで何の気なしに、「悪い大人を見つけたらどうするの?」と尋ねると、博之は子供とは思えない真剣な顔つきでこう答えたのだった…。
《続きは追記に》。